なぜ今「関係主体幸福度」が必要なのか?マイスター高等学院が育てる21世紀型人材の本質
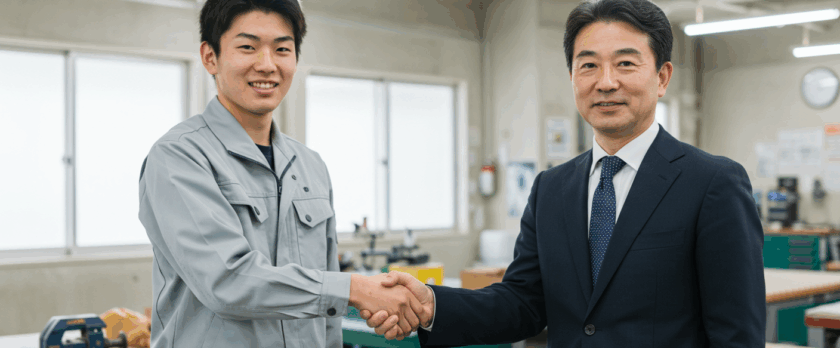
はじめに:日本が直面する労働者不足という危機
皆さんは、地域の大工さんや職人さんが足りないという話を聞いたことはありませんか。実は今、日本全国で深刻な「労働者不足」が起きています。建築現場、製造業、介護施設、農業、飲食店など、あらゆる現場で人手が足りず、地域産業が危機に瀕しているのです。
この問題を解決するには、単に「働く人の数」を増やせばよいのでしょうか。答えは「いいえ」です。必要なのは、専門技術を持ちながら、同時に社会や他者との関係性の中で高い価値を生み出せる人材です。マイスター高等学院では、このような人材を「マイスター」と呼び、育成に力を入れています。
マイスター高等学院は「日本を守る人材育成の場」として設立されました。大工や製造業、福祉・介護、農業、飲食業などの現場実務者として働くための技術と、「志と人間力」を統合的に学べる通信制の学校です。
この教育の中心にあるのが「関係主体幸福度」という考え方です。聞き慣れない言葉かもしれませんが、これこそがこれからの時代に最も必要とされる価値観なのです。本記事では、この「関係主体幸福度」とは何か、そしてなぜマイスター育成に欠かせないのかを、できるだけわかりやすく解説していきます。
「関係主体幸福度」って何?共益という新しい価値観
従来の幸福度との違い
「幸福度」と聞くと、多くの人は「自分が幸せかどうか」という個人的な満足度を思い浮かべるかもしれません。また、企業の文脈では「顧客満足度」や「従業員満足度」という言葉もよく使われます。しかし「関係主体幸福度」は、これらとは少し異なる概念です。
一般社団法人日本未来企業によって定義される「関係主体幸福度」とは、「個人や組織単位で認知・享受される価値で、双方向的な『共益』に係る幸福度」のことを指します。
ここで重要なキーワードが「共益」です。共益とは、関係主体間の共通の利益や幸福を意味します。つまり、自分だけが得をするのでもなく、社会全体という漠然とした対象でもなく、「具体的な関係性を持つ人々や組織が一緒に幸せになる」という考え方なのです。
公益、共益、私益の違い
ここで3つの「益」について整理しておきましょう。
「公益」とは、広く社会全体に対して効果や影響が及ぶ利益のことです。例えば、環境保護活動や災害支援などは公益に当たります。不特定多数の人々のための活動です。
「私益」とは、個人や企業自身の利益のことです。企業でいえば、継続・成長に必要な経済的達成度のことを指します。利益を上げなければ企業は存続できませんから、私益の追求も決して悪いことではありません。
そして「共益」は、その中間に位置します。従業員、顧客、取引先、地域など、特定の関係主体が認知し、享受する幸福度です。お互いに顔が見える関係の中で、共に幸せになることを目指すのです。
マイスター高等学院が育成を目指す「人間力」は、まさにこの共益を実現するために不可欠な能力です。現場実務者であるマイスターは、専門技術を使って個々の顧客や同僚、地域といった関係主体の幸福度を高める役割を担います。
双方向性が鍵:一方通行ではない価値の交換
これまでの企業と従業員の関係
従来の企業と従業員の関係を考えてみましょう。多くの場合、企業が従業員に給料を支払い、従業員は労働を提供するという一方通行の関係でした。もちろん表面的には双方向に見えますが、実際には「企業が主で従業員が従」という上下関係が暗黙のうちに存在していたのではないでしょうか。
顧客との関係も同様です。企業が商品やサービスを提供し、顧客はお金を払う。それだけの関係性で終わってしまうことがほとんどでした。
関係主体幸福度が示す新しい関係性
「関係主体幸福度」の定義で最も革新的なのは、その価値が「双方向的」であるという点です。つまり、企業から関係主体への提供だけでなく、個人や組織側からも企業に価値を提供することがあるのです。
これは単なる理想論ではありません。関係主体自身が積極的に企業活動に貢献し、相互に幸福度を高め合うという、まったく新しい企業のあり方を示しています。
例えば、マイスター高等学院の生徒を考えてみましょう。生徒は単なる「教育を受ける側」ではありません。学院を運営する企業と3年間の有期雇用契約を結んで働きながら学びます。つまり、生徒は企業の一員として価値を提供する側でもあるのです。
生徒は労働力を提供し、技術習得への意欲を持ち、「志と人間力」を発揮して企業の生産性向上に貢献します。一方、企業は生徒に適切な労働環境、福利厚生、収入、そして専門技術の指導を提供します。
このような双方向的な価値交換の中で、生徒は「自分の働きが他者の幸福に貢献している」という実感を得ることができます。これが「関係主体幸福度」の本質であり、人間力を育てる最良の環境なのです。
マイスター高等学院の教育モデル:働きながら学ぶ意味
3年間の有期雇用契約という実践の場
マイスター高等学院の最大の特徴は、生徒が学院を運営する企業と3年間の有期雇用契約を結んで働きながら学ぶという点です。現在、生徒が在籍する大工コースでは、建築現場で実際に働きながら職業教育を受けています。
なぜこのような仕組みが必要なのでしょうか。それは、教室での座学だけでは「関係主体幸福度」を実感できないからです。実際に働き、お客様と接し、同僚と協力し、時には失敗もしながら学ぶことで、初めて「共益」の意味が腹に落ちるのです。
ある生徒は、初めて担当した現場でお客様から「ありがとう」と言われた時、自分の仕事が誰かの幸せに直結していることを実感したと話していました。これこそが双方向的な価値提供の瞬間です。
企業から生徒への価値提供
マイスター高等学院を運営する企業は、生徒に対して以下のような価値を提供しています。
まず、安全で働きやすい労働環境です。未来創造企業として認定されている企業は、福利厚生や就業条件、労働環境において一定の基準をクリアしています。生徒は安心して働ける場所で技術を学べるのです。
次に、収入です。働きながら学ぶことで、生徒は経済的に自立しながら教育を受けられます。これは特に家庭の経済状況が厳しい生徒にとって大きな支援となります。
そして最も重要なのが、専門技術の指導と人間力の育成です。熟練の職人から直接技術を学び、現場で求められる協調性、コミュニケーション能力、責任感を培うことができます。
生徒から企業への価値提供
一方で、生徒も企業に対して価値を提供しています。若い労働力は企業にとって貴重です。特に労働者不足が深刻な建築業界では、若手の存在は現場を活性化させます。
また、技術習得への強い意欲を持つ生徒の姿勢は、他の社員にも良い刺激を与えます。「教えることで学ぶ」という言葉があるように、生徒を指導する過程で、先輩社員も自分の技術や知識を再確認し、向上させることができるのです。
さらに、マイスター高等学院の生徒は「志と人間力」を育てる教育を受けています。倫理観や人間関係のあり方を学ぶために、授業では『論語物語』が推奨されています。このような教育を受けた生徒は、単なる技術者ではなく、企業文化を体現し、継承していく存在となります。
卒業後の正社員転換という未来
マイスター高等学院の生徒は、卒業後に学院を運営する企業に正社員転換して就職することを目標としています。これは「学生時代から一貫して運用されるキャリア」を意味します。
多くの学校では、卒業後の就職活動で初めて社会と接点を持ちます。しかしマイスター高等学院の生徒は、学生時代から同じ企業で働き続けるため、企業文化や仕事の流れを熟知した状態で正社員になれるのです。
この一貫性は、生徒にとって大きな安心材料となります。また、企業にとっても、3年間かけて育てた人材をそのまま正社員として迎えられるメリットがあります。これもまた、双方向的な価値提供の好例といえるでしょう。
持続可能な経営と幸福度の好循環
社員の幸福度が生産性を高める
「関係主体幸福度」は単なる精神論ではありません。これは企業の持続可能な経営の基盤となる、極めて実践的な概念なのです。
未来創造企業認定が持つ価値の一つに「企業力のアップ・持続可能な企業としての価値」があります。これは、関係主体との信頼により持続可能な経営を行うことができ、その結果として具体的な成果が生まれることを示しています。
特に重要なのが、従業員の幸福度と生産性の関係です。研究によれば、幸福度の高い社員は、より高いエンゲージメントを持ち、結果として生産力が増すことが明らかになっています。
マイスター高等学院の生徒は、この幸福度の高い環境で技術を習得し、働く経験を積みます。周囲の社員が生き生きと働いている姿を見ることで、「自分もこのように長く働き続けたい」と思えるのです。
生産力向上が企業の成長を支える
社員の幸福度が高まり、生産力が向上すると、企業の経済的達成度も高まります。これは「社会・経済的価値」、つまり企業の継続・成長に必要な「私益」の追求に貢献します。
ここで重要なのは、「私益」を追求することは決して悪いことではないという点です。むしろ、企業が経済的に安定していなければ、社員の雇用も守れませんし、社会貢献活動も継続できません。
ただし、従来の企業のように私益「だけ」を追求するのではなく、「公益」「共益」「私益」のバランスを取りながら経営することが、未来創造企業の特徴なのです。
採用と定着率の向上がもたらす安定
関係主体幸福度の高い企業は、外部からも魅力的に見えます。「働きたい企業としての価値が高まり、採用や定着率の高まりに繋がる」のです。
これはマイスター高等学院の卒業生にとって極めて重要な保証となります。社会貢献が実現でき、安心して働ける会社として認知されている企業への就職は、キャリアの安定性に対する強い信頼を提供します。
また、高い定着率は、社員が長期にわたって安心して働き続けられる環境であることを意味します。若い世代にとって、「この会社で長く働けるだろうか」という不安は大きなものです。しかし、マイスター高等学院の卒業生は、学生時代から一貫して同じ企業で働いているため、その不安が最小限に抑えられるのです。
さらに、定着率が高い企業では、ベテラン社員が多く残るため、技術やノウハウの継承がスムーズに行われます。マイスターは、安定した環境で長期的に専門技術を磨き、地域産業の担い手としての役割を全うできるのです。
公益・共益・私益の統合:未来創造企業の全体像
7分野の指標が示す総合的な価値
未来創造企業認定は、「これからの21世紀型企業としての価値」を持つ企業を認定する制度です。その評価は、「地球」「社会」「地域」「顧客」「取引先」「従業員(家族)」「経営者」という7分野の指標に基づいて行われます。
この7分野は、それぞれが公益、共益、私益のいずれかに関連しています。例えば「地球」「社会」は公益に、「顧客」「取引先」「従業員(家族)」は共益に、そして「経営者」は私益に関連する指標です。
未来創造企業は、この7分野すべてにおいてバランスの取れた取り組みを行っている企業なのです。つまり、一つの価値だけを追求するのではなく、総合的に社会に貢献する企業であることが求められます。
公益と共益の相互作用
「社会的価値」とは「広く社会全体に対して効果・影響が及ぶ、公益に係る価値」のことです。未来創造企業は、本業を通じて地域産業の課題、例えば労働者不足などを解決することで公益に貢献します。
しかし、この公益の活動を支えているのが「関係主体幸福度」、つまり共益なのです。社員や取引先、顧客が幸福でいること(共益)は、企業活動を安定させ、結果として、より大きく、継続的に社会全体への貢献(公益)を可能にします。
マイスター高等学院の生徒が「地域産業を担い、労働者不足が加速する日本の未来を変える」という大きな志を持つことは、この公益追求の意識の表れです。しかし、その志を実現するためには、まず目の前の顧客や同僚、地域の人々との関係性の中で共益を実現することが必要なのです。
SSC(サスティナブル・ソーシャル・カンパニー)という目標
未来創造企業が目指すのは、SSC(サスティナブル・ソーシャル・カンパニー)、つまり「持続可能な社会的企業」です。これは、経済的に持続可能であると同時に、社会的にも持続可能な企業を意味します。
従来の企業は、経済的な持続可能性だけを重視してきました。しかし、それでは社会や環境への負荷が大きくなり、長期的には企業自身も存続が危うくなります。
一方、社会貢献だけを重視して経済的に立ち行かなくなる企業も問題です。どんなに素晴らしい理念を持っていても、倒産してしまえば何の意味もありません。
SSCは、この両方をバランスよく実現する企業モデルなのです。そして、このSSCで働くマイスター高等学院の卒業生は、社会変革の担い手として、高い権威性を持ってキャリアを遂行できるのです。
まとめ:共益を創造するマイスターの未来
「関係主体幸福度」とは、「共益」に係る双方向的な幸福度のことです。これはマイスター高等学院が育成する「人間力」が最も実践されるべき土壌であり、これからの時代に最も必要とされる価値観です。
マイスター高等学院の生徒は、3年間の有期雇用契約を通じた実務経験の中で、自らが企業と社会に対して価値を提供する双方向性を学びます。単なる知識の受け手ではなく、価値の提供者として成長するのです。
この過程で培われる「人間力」は、技術と並んで、マイスターにとって最も重要な資質となります。専門技術だけでは、関係主体の幸福度を高めることはできません。コミュニケーション能力、協調性、責任感、そして倫理観。これらすべてが統合されて初めて、真のマイスターとなれるのです。
未来創造企業における関係主体幸福度の追求により、社員の幸福度が高まり、生産力が増し、採用や定着率が高まるという持続可能な好循環が生まれます。マイスター高等学院の卒業生は、この揺るぎない信頼性と権威性を持つ環境で、技術と「志と人間力」を最大限に発揮します。
2026年4月には第1号生が誕生する予定です。彼らは、地域産業の担い手として、そして社会全体の「関係主体幸福度」を高める存在として、日本の未来を変える役割を担っていくことでしょう。
労働者不足という危機は、見方を変えれば、若い世代にとって大きなチャンスでもあります。マイスターとして専門技術と人間力を身につければ、社会から必要とされる存在として、安定したキャリアを築くことができるのです。
そして何より、自分の働きが他者の幸福に貢献しているという実感は、どんな金銭的報酬にも代えがたい喜びをもたらします。これこそが「関係主体幸福度」の本質であり、マイスター高等学院が目指す教育の到達点なのです。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。







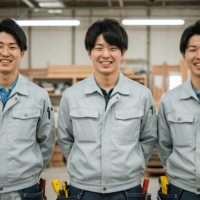













この記事へのコメントはありません。